


南海日日新聞掲載分 |


【注意】喜界島酒造では製造しておりません。
|
|


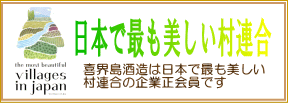 |
  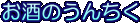  
(其之36)
中国のお酒の伝説④

中国の5種類のお酒、4つ目は果酒です。
葡萄酒(ブウタオチュウ)など果実を醸造する酒と、果実を漬け込んで味わいを出したリキュール類が古くから造られて果酒(クオチュウ)と呼ばれています。桃、杏子、サンザシ、ライチなど、多数の果実が薬酒に用いられていますが、ワインはそれほど普及せず、白酒に杏子の果実を漬け込んだ「杏露酒」(シンルチュウ)などが日本では有名です。20世紀以降、中国でも多くのワインが飲まれるようになり、西域を中心に多数の中国ワインが造られています。
中国の5種類の最後のお酒はビールです。ドイツ人が1903年に租借地の青島にビール会社を設立したのが始まりで、現在、中国ビール生産は世界代2位を誇っています。 |
|

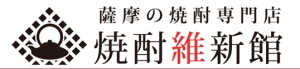
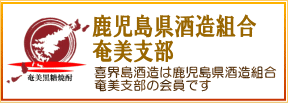
|
|

